※当記事はアフィリエイト広告を利用しています
私は「いい母親でいたい」という想いが強い方だと思う。
また、「親の態度や声かけが強く子どもに影響する」とも思っていて、ゆえに、子どもが情緒不安定になったり、何かにつまづいていたりすると「自分がなんとかしなくちゃ」「自分のせいで」と、今思うとだいぶ窮屈な子育てをしてきたと思う。
HSP気質の私とHSC気質の娘は、お互いに空気を読み、どちらかの感情に振り回されながら過ごすことも多い。
それは、居心地の良い関係とは言えないかもしれない。
そんな私の子育ての窮屈な考え方を変えてくれたのは、黒川伊保子さん著書の『母脳』を読んだ時だった。
『母脳』は、黒川伊保子さんの子育てを脳科学の視点から深く考察しており、同じ母親として共感する部分も多いし、いろんなことに気づかせてくれる著書だ。
中でも『母親の直感はいつでも正しい』という部分が特に印象に残っている。
私は「子どものために」いろいろなことを子育ての中で選択してきた。
それが正しいとか間違っているとか誰も教えてくれないし、教えてくれるはずもない。だから苦しい。子育ては孤独だ、と辛かった時もある。
そして、後から考えて「あれは正しかったのか」「あの時ああしていれば」と、後悔もする。
でも、『母脳』に『母の選択はいつも正しい』と教えられ救われた。
子どものことを愛し、子どもの最善を常に考えている母親の直感、選択は間違っていない。
私は「親の影響」をとても恐れていたし、それ故、育児をする上で緊張感もあった。
その緊張感は、危険察知という意味では役に立ったかもしれないが、「大らかである」とは反対ではあるために、窮屈な育児になっていたかもしれない。
でも、子どもにとって「親の影響」は必ず受けるもの。
特に「母親の影響」は避けたくても避けられないもの。
影響することを恐れすぎて、私のような窮屈な育児をしてはいけない。
ある程度影響することは承知の上で、子どもがどんな人間になっていくのか成長の過程を楽しもうと『母脳』を読んで私は解釈した。
脳の発達に『読み聞かせ』の重要性や他にも大事なことも書かれており、大変勉強になる著書だ。
私の子育ての「バイブル本」として繰り返し読みたい本になった。
育児をする上で行き詰まったり、苦しくなった時にはこの本を読んで、また大事なことに気づきたい。
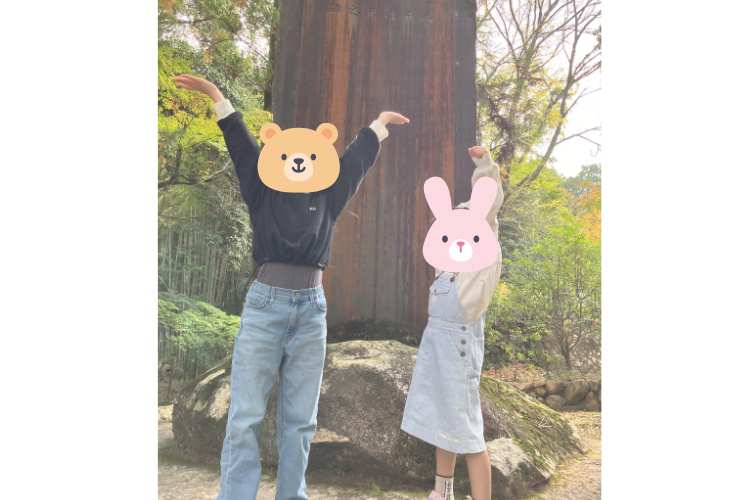
さて、最近「これはダメだな」と思ったことがあって。
娘が頑張っている体操の習い事。
スポーツする上では避けられないけれど、やはり「〇〇ちゃんよりも出来ていない」「〇〇ちゃんよりは出来ている」と『比較』してしまう。
他人との比較はモチベーションを上げるためやライバル意識を上げて自らの技術を向上するのには役に立つかもしれないが、親としてそればっかりだとダメだな、と。
どうしても周りに目がいってしまう私は、娘に直接言わなくても、おそらく伝わってしまうと思うし、娘の向上心が低いなと思うとどうしても口に出してしまう時もある。
その思考が強くなってきて、娘に求めることが「〇〇ちゃんよりも上手になろう」になっていた時に、娘の顔は曇っていく。
今まで出来ていない技ができた時に「これで〇〇ちゃんに追いついた」と、それはある意味嬉しいが安堵に近い。
それではいけない、何を見ているんだろうと負のループに気づいた私は、
「他人との比較」ではなく「過去の娘との比較」を大事にしなくちゃと自分で自分を戒めた。
そう、「今まで出来なかったけど、出来てすごい!いっぱい練習したからだね、嬉しいね!」とか「今はできないけど、何度も練習してできるようになろう」と意識的に伝えてみる。
娘は嬉しそう。
人生において大切なのってこういうことだよね。
これからの人生、比較したりされたりすることってたくさんあるけど、大人になってもそれに押し潰されることなく、「昨日の自分よりもできた自分」や「自分の立てた目標を達成できた自分」を大切にしてほしい。
親が教えられることってこういうことなんかな。って。
大切なことに気づいたという話でした。




